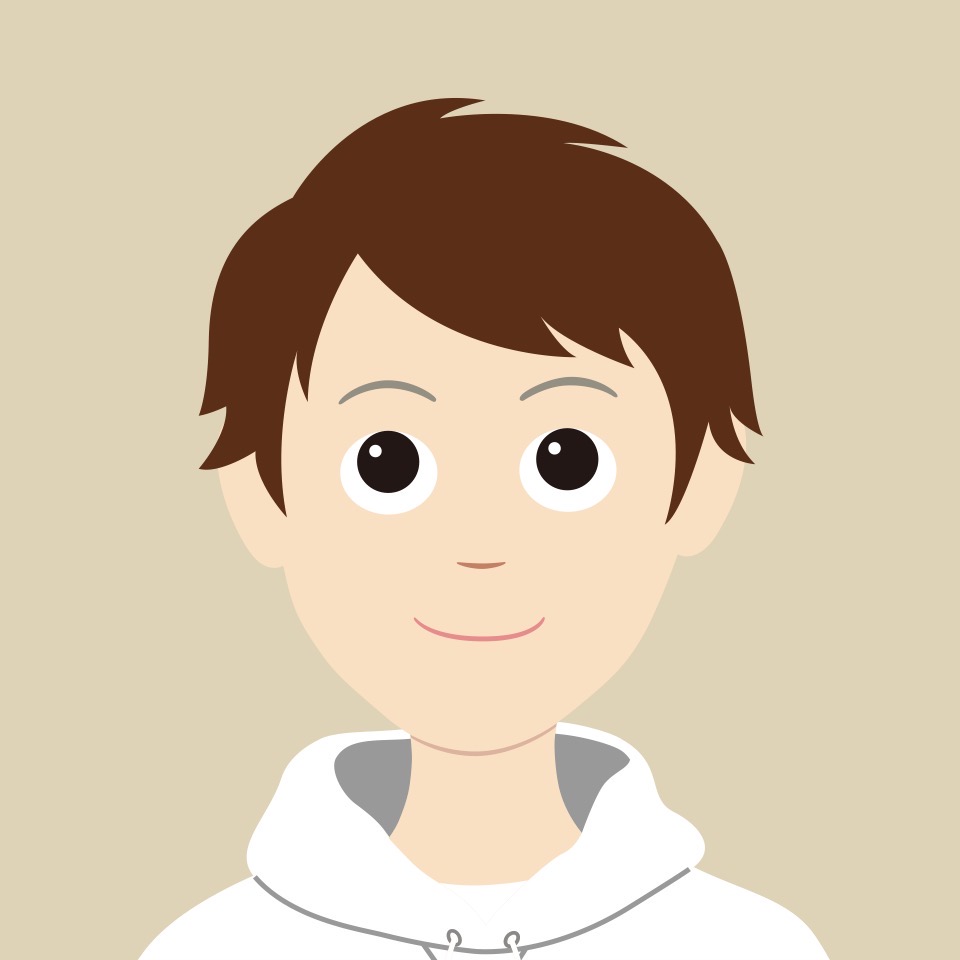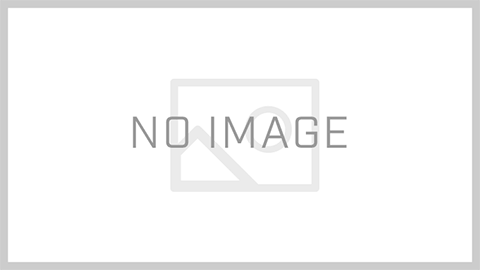近年ではヘアカラーのアレルギー(以後:ジアミンアレルギーと呼ぶ)は増加傾向にあります。
カラー剤の一般化が進み自宅で簡単に染めることができるようになったことや、低価格で染めることができる美容院が増加し染める回数が短期化することでひと昔前よりもヘアカラーに触れる回数が増えたことが原因として考えられています。
こうした背景からジアミンアレルギーの認知も進み、テレビや雑誌でも取り上げられる機会が増えてきたと考えています。
この記事ではそんなジアミンアレルギーの特徴を正しくお伝えしつつ、まだ発症されていない方に向けて予防方法を解説していきます。
ジアミンアレルギーの方と向き合ってきた経験を生かしてpopoliaというブランドが独自に確立している予防方法を参考にしてみてください。
パッと読める目次
ジアミンアレルギーとは?
ジアミンアレルギーとはヘアカラーの成分に含まれる『ジアミン』と言う成分に対して発生するアレルギーのことを言います。
発症する過程は花粉症などと似ていると言われており、ジアミンとの接触を繰り返す中で許容量を超えるとアレルギーを発症します。
ジアミンアレルギーは1度発症すると完治することはないので、発症しないように取り組むことが重要です。
無理をして染めようとしてしまうと初回よりも2回目、2回目よりも3回目と症状が重くなっていきます。
どんな症状が出るの?
ジアミンアレルギーの前兆として染めている間に痒みをはじめとした刺激を感じたと体験している方が多いように感じます。
発症後は染めている間よりも帰宅後〜翌朝頃から痒み・腫れ・炎症・皮膚のつっぱりなどの症状を感じ始め2日間ほどかけて徐々に悪化していきます。
反応が強く出ている方の場合は頭だけでなく、顔や首、耳と言う周りの部位にも同様の症状が現れることもあります。
違和感を感じたらなるべく早いタイミングで皮膚科やアレルギー科などを受診し医師の処置を受けるようにしてください。
事前に調べる方法もある
ここまでの解説を見てもしかしたら私も・・・。と感じた方はアレルギー反応を事前に調べてから染めるようにしましょう。
『パッチテスト』と呼ばれる方法で反応の有無を調べておくことで突然のアレルギーによるトラブルを回避することができます。
主に皮膚科やアレルギー科のある病院や美容院でテストを受けることができます。
ただし場所によってはパッチテストを行っていないところやカラー剤を持ち込む必要があるところがあるので事前に確認をしておくようにしましょう。
ジアミンアレルギーは予防することが大切
まずジアミンアレルギーの前提条件として発症後に直すことができません。
アレルギーを改善しようと取り組んでもできることがないと言うのが現状です。
もしこの記事を読んでいるあなたがまだアレルギーを発症していないのであれば今すぐにでも予防を始める必要があります。
この記事で1番重要なポイントを解説していきます。
ジアミンアレルギーの予防に有効な取り組みは次の3点です。
- 頭皮を健康な状態に保つ
- 毎回のヘアカラーでの負担を減らす
- 年間でのジアミンとの接触回数を減らす
これらを取り組むか否かで将来の発症リスクは大きく差が開きます。
頭皮を健康な状態に保つ
頭皮にはもともと外からの刺激から身を守るためのバリア機能が備わっています。
ヘアカラーの刺激はもちろん乾燥や紫外線などダメージとなりえる原因をブロックしてくれています。
しかし頭皮に負担が大きくかかってくるとこのバリア機能は低下していきます。
年齢が上がるごとにジアミンアレルギーの発症率が高くなるのは徐々にバリア機能が衰えていくことが原因の1つです。
頭皮の健康を維持するためには保油、保湿、最適なシャンプー選びを行うことが重要です。
popoliaではこれら3つのバランスを適性に保てるように4つの頭皮ケアアイテムを展開sっております。
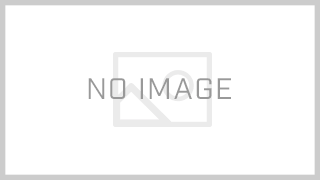
毎回のヘアカラーでの負担を減らす
ヘアカラーとの接触はジアミンアレルギーを発症する1番の原因です。
- カラー前には頭皮を保護する
- 頭皮には薬剤をべったりとつけない
- カラー後に頭皮に薬剤を残さない
この3つは徹底する必要があります。
popoliaシャンプーはカラー後1ヶ月使用することで頭皮に残ってしまう薬剤を完全除去するように設計されております。
年間でのジアミンとの接触回数を減らす
例えば20歳から70歳までヘアカラーを続けると過程します。
1ヶ月に1度のペースで染めていればこの50年の間に600回染める計算になります。
始めにも解説しましたがジアミンとの接触回数が増えれば増えるほどにアレルギーの発症率は高くなります。
そこで1年間当たりのヘアカラーの回数を減らすことがジアミンアレルギーの予防には効果的と言えます。
例えば月に1度のペースで髪を染める方の場合はヘアカラーとヘアカラーの間にノンジアミンカラーを挟むことで接触回数を減らすことができます。
あるいは毎回使用しているヘアカラーとノンジアミンカラーを組み合わせて低ジアミンカラーを作り出せば1回当たりのヘアカラーのジアミン濃度を下げることができます。
これらは1つの例に過ぎませんが、このような取り組みを行うことで生涯でジアミンとの接触する回数を減らすことができ結果的にはジアミンアレルギーの予防に大きく貢献すtることができると考えております。
ジアミンアレルギーを発症した後に髪を染めることはできないの?
しっかりと予防をしていてもヘアカラーを行う以上はリスクを0にすることはできません。
または既にジアミンアレルギーを発症してしまった方の場合は髪を染めることはできないのでしょうか?
実はアレルギーを発症された方に向けてノンジアミンカラーといったジアミンを含まない専用のカラー剤も存在します。
ノンジアミンカラーの種類は全部で6つあります。
- アルカリカラー
- トリートメントカラー
- ヘアマニキュア
- ライトナー
- ブリーチ剤
- 天然のヘナ
髪の状態や仕上がりのイメージに合わせてこれらを使い分けることでジアミンアレルギーに悩む方でも髪を染めることができます。
ただしノンジアミンカラーであってもジアミン以外の成分に対してアレルギー反応が出る可能性や刺激を感じる可能性もあります。
既にジアミンアレルギーを発症されている方は肌も敏感な状態なので使用前にはパッチテストなどを行い慎重に染めていくようにしていきましょう。
まとめ
- ジアミンアレルギーは発症後にできる改善策はないので常に予防をする必要がある
- 健康な頭皮を保ち、ヘアカラーとの付き合い方を見直すことが予防の近道
- 万が一ジアミンアレルギーを発症した場合にはノンジアミンカラーという専用の薬剤がある
ヘアカラーを行う上で気にするべきは“今”ではなく“未来”です。
今、負担がかかることをしていれば、そのしわ寄せは将来必ず訪れます。
その時に後悔をしても取れるべき改善策は残されていません。
特別悩むことのない若いうちから将来に向けてアレルギーケアという投資を行うことが健康な頭皮や髪を維持する秘訣です。